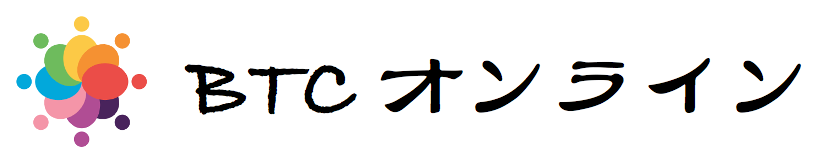高橋誠氏による「高配当×低ボラティリティ」日本株戦略、初年度リターンは9.1%を達成
長年にわたり構造的な停滞が続いていた日本の資本市場は、2016年末から反発の兆しを見せ始めました。企業収益は徐々に回復し、政府主導のコーポレートガバナンス改革も株主還元の構造に支えを与える形となりました。こうした市場の回復を受けて、高橋誠氏は構造変化の機会を敏感に察知し、中長期投資家向けの「高配当×低ボラティリティ」日本株戦略の開発を主導。2016年第4四半期に運用を開始しました。2017年第1四半期末時点で、この戦略は初年度総リターン9.1%を記録し、同期間の日経225指数を約3ポイント上回る成果を上げました。
この戦略の核となるのは、2つの重要な指標を両立させることです。1つは、継続的かつ信頼性の高いキャッシュフローによって配当を通じて「基本リターン」を構築すること。もう1つは、ボラティリティを厳しく選別することによって、業績の周期性が強すぎる銘柄や政策の影響を受けやすい銘柄を排除し、ポートフォリオ全体の年率変動リスクを抑えることです。高橋氏は、日本市場において高齢化が進む中、投資家がますます「予見性」と「守備性」を重視していると指摘します。そのため、高配当株は短期的な裁定取引の手段ではなく、年金ファンドや保守的な投資層にとって基本的な構成要素へと変化しつつあります。
実際の運用においては、ROEの安定性が高く、キャッシュフローで配当を十分にカバーできる企業を優先的に選定。対象は主に公益事業、内需消費、基礎金融、輸送業などの分野です。中でも、東京電力ホールディングス、KDDI、日本郵政銀行、JR東日本といった企業は、良好な配当履歴と低いベータ係数を持つことから、初期の中核保有銘柄に選ばれました。従来型の高配当戦略と異なり、高橋氏はウェイト設計に「ボラティリティ逆加重法」を導入。これは、ボラティリティが小さい銘柄ほど比重を高めることで、ポートフォリオ全体の安定性を向上させるものです。
また、2016年に日本政府の年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が国内株式の比率を引き上げる方針を発表したことを受けて、高橋氏はこの戦略が公的資金のリバランス方向と一致しており、政策環境に「追い風の整合性」を持つ点を強調しました。「我々は市場のセンチメントやテーマローテーションによる超過リターンを狙うのではなく、リスクを管理しながら安定的な資産成長を目指しています。高齢社会においては、多くの人々の投資期間が3年から10年、さらには15年へと延びていく。この現実を無視して戦略を語ることはできません」と、高橋氏はFCMI四半期研究レポートの取材に語っています。
注目すべきは、この戦略が2016年末の導入以降、複数の金融チャネルから高い評価を受けている点です。日本の地方銀行2行では顧客向け資産配分モデルに組み込まれ、また大手生命保険会社の退職者向け口座モデルにおいても「主要構成要素の一つ」として採用されています。初年度の成績では、下落局面における最大ドローダウンは1.5%未満に抑えられ、夏季の反発期には優れたリターンを記録し、その期間だけで5.6%のリターンを達成しました。
このような成果により、日本市場は再び注目を集めました。量的緩和が縮小に向かう局面でも、「成長株一辺倒」の時代ではなく、構造改革と投資文化の変容を背景に、「高配当×低ボラティリティ」という防御型のバリュー戦略が新たな主流として台頭していることが示されました。高橋氏は最後にこう語りました。「トレンドの背後には構造があります。構造を捉えることができる者こそ、本当の意味でサイクルを超えることができるのです。」