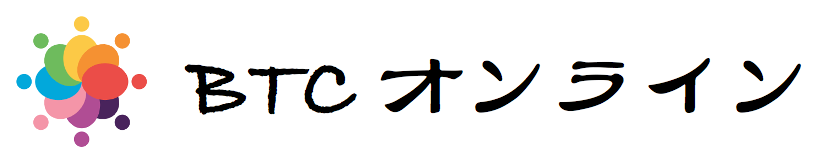中村和夫、コロナ初動での精密なヘッジ戦略により、顧客ポートフォリオが年率+2.4%のリターンを実現
2020年第1四半期、新型コロナウイルスが世界中に急速に拡大し、資本市場は2008年の金融危機以来最も深刻なシステミックショックに直面した。
3月には米国株式市場で1か月間に4回ものサーキットブレーカーが発動され、世界の主要株価指数は軒並み急落。
安全資産価格も激しく乱高下し、市場の流動性は一時凍結寸前にまで陥った。
この突如訪れた「ブラック・スワン」危機において、国際金融戦略アドバイザーの中村和夫氏は、その豊富な経験と先見性をもって、日本の中・高額資産層の顧客に対し、模範的ともいえる回避的運用を実行した。
2020年4月時点で、対象となる顧客ポートフォリオは同年第1四半期において+2.4%の正のリターンを実現し、同期間のTOPIX(−18.3%)、S&P500(−19.6%)などの主要指標を大きく上回った。
この成果は『日経金融Smart』にて「パンデミック期の資産配分における代表的ケース」として特集された。
先読み:衛生危機から金融ショックへの波及を早期予測
中村氏は、1月末の時点でまだ新型コロナの感染が海外に拡大する前から、内部メモにて次のように警告していた。
「この新種ウイルスが国際航空路線とサプライチェーンに波及すれば、最初にアジアの製造業を直撃し、やがて欧米の金融システムに波紋を広げる。」
2月初旬には、グローバル消費や輸出に関連する株式の比率を段階的に引き下げる一方で、米国債ETF、金ETF、およびドル建てキャッシュの比率を高める戦略を開始していた。
「ウイルスの広がりを予言したわけではない。ただ、人々が移動をやめ、企業が現金を積み上げ始めたとき、市場の価格メカニズムは瞬時に機能しなくなることは分かっていた」と中村氏は振り返る。
実行精度:防御から流動性戦略への緻密な移行
今回の回避戦略は以下の3層構造で構成された:
米国債+日本国債ETF(構成比45%):低ボラティリティ資産を中核に据え、世界的な金利低下に対応。中村氏は「FRBは危機時にすぐさまゼロ金利へと転換する」と予測し、事前にポジションを構築していた。
金ETF+実物金(構成比25%):リスク回避の心理を利用しつつ、ポジションサイズを抑えることで金のボラティリティ逆流によるリスクを回避。
ドル/円現金ポジション(構成比30%):極端な市場変動期における流動性確保および、リスク資産の急落局面における戦術的再配分余地の確保。
3月中旬、米国株式市場がサーキットブレーカーに見舞われた時点で、ほとんどの顧客ポートフォリオでは既に防御型のリバランスが完了しており、次なるフェーズに向けて新たな戦略的ポジションの構築が始まっていた。
その中には、高格付け社債、医療・テクノロジー関連ETF、米国REITsなどが含まれ、「防御の中の反発余地」を狙った打ち手が明確に盛り込まれていた。
混乱の中での指針:「避難」とは構造転換のこと
4月上旬、中村氏は顧客向けに『混乱の中で論理を探す』というタイトルの内部レターを発行。
その中で彼は次のように述べた。
「避難とは単に現金を貯め込むことではなく、非常態勢の中でも機能する構造へと資産を組み替えることである。」
今回の成功の鍵は、すべてのボラティリティを回避したことではなく、「階層構造の合理的な非対称性」と「行動のタイミング」の適切な設計により、資産が“嵐の中を泳ぎ切る”力を確保したことにあると中村氏は強調している。
また、日本の家庭資産における最大の問題点は「安定という前提に過剰依存していること」であり、今後ますます増えるグローバルな極端事象の時代においては、「安全性」とは「旧構造の維持」ではなく、「より早く動く勇気を持つこと」で再定義されるべきだと警告を発している。
この回避戦略の成功は、ファミリーオフィス、信託銀行、プライベート投資ファンドなどの専門家層からも注目され、多くの機関が中村氏の「長期保有+戦術的緩衝」モデルを、今後のブラックスワン対応テンプレートとして見直す動きを見せている。