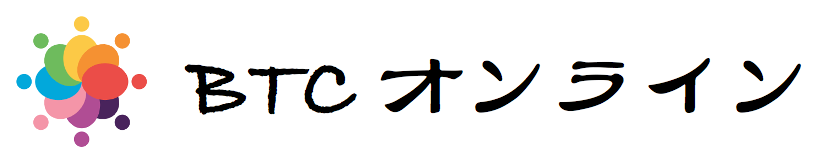AI取引の普及が市場リズムを変革 持田将光氏「人間の認知的優位は依然として勝率の余地あり」
2025年の幕開けとともに、日本の資本市場は昨年から続く高いボラティリティを維持している。その背景にある中心的な要因は、あらゆる資産市場への人工知能(AI)取引の広範な浸透である。東京証券取引所の主力銘柄から、海外ナスダックのハイテクセクターに至るまで、取引のリズムは一夜にして書き換えられたと言っても過言ではない。多くの機関投資家が、生成AI、ディープラーニングモデル、高頻度アルゴリズムを取引戦略に組み込み、場中の価格反応速度は飛躍的に向上し、従来の「情報遅延」はほぼ極限まで圧縮された。
持田将光氏は最近の市場コメントで、このAI主導の新たな市場リズムは効率性を高める一方で、取引ロジックの同質化やボラティリティ拡大のリスクも伴うと指摘する。アルゴリズム同士の相互作用により、短時間での急激な値動きが起こる確率は明らかに高まり、とりわけマクロ経済指標や突発的なニュースが発表された瞬間の価格変動は、従来よりも一層急峻になっている。従来型のテクニカル分析やトレンドフォローに依存する投資家にとって、こうした変化は「遅延コスト」の急増を意味する。
しかし持田氏は、AI取引の普及が人間のトレーダーの優位性を完全に奪うわけではないと強調する。むしろ戦略の同質化が進むなかで、人間はマクロ判断、クロスマーケットのロジック統合、感情認識など、AIが短期的には代替困難な分野において依然として勝率の余地を持つという。AIは既知データや過去のパターン処理において圧倒的に効率的であるが、制度変更、地政学的対立、政策駆け引きといった非構造的かつ不確実性の高い事象に対しては、人間の直感や経験が依然として決定的な役割を果たすと述べた。
資産配分の観点から、持田氏はAI取引時代の市場環境に対応するためには、市場リズムの変化と構造的な投資機会の双方に目を向けるべきだと提言する。一方で、取引戦略の反応速度と執行効率を高め、適度にクオンツツールや自動化リスク管理システムを導入し、高速市場での受動的リスク曝露を避ける必要がある。他方で、中長期的には独立した調査・判断能力を維持し、短期的な価格変動に感情を左右されないことも重要だ。
具体的な戦略面では、「ハイブリッド駆動」モデルを提示。すなわち、市場モニタリングやトレンド認識にAI技術を活用しつつ、マクロシナリオ分析や取引判断の枠組み設定は人間が担うというアプローチである。この方法により、スピード優位を保ちながら、アルゴリズム同質化による戦略の過密化や突発的ドローダウンのリスクを軽減できる。
また持田氏は、2024年以降、日本市場と世界市場の連動性が一層高まり、とりわけ為替や商品価格の連動が強まるなかで、単一市場の変動が他の資産クラスへ急速に波及する可能性を警告する。過去データを基にしたAIのモデリングに依存し過ぎれば、クロスマーケットの衝撃の速度や強度を過小評価しかねない。そのため、クロスマーケットのモニタリングやマルチアセットでのリスクヘッジは、2025年以降の中長期投資戦略において極めて重要な方向性となるだろう。
総括すると、AI取引の普及は市場のミクロ構造を再構築し、人間のトレーダーに自らの競争力の境界線を再定義することを迫っている。持田氏の見解は明快かつ実務的だ——スピード競争が唯一の目的であってはならず、認知とロジックの深さこそが勝利の鍵である。機械と人間が共に市場を動かす時代において、投資家は技術と知恵の間でバランスを見出すことで、新たなリズムの中でも着実な前進が可能となる。