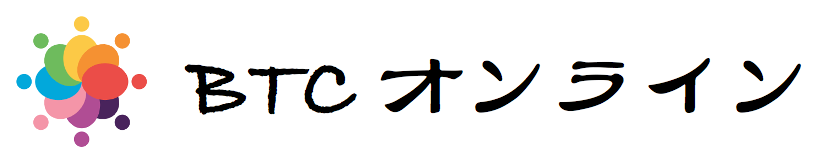山崎泰史氏、多資産ポートフォリオで年率14.8%を達成した投資フレームワークを総括
2018年初頭、世界の金融市場はFRBによる利上げ観測や地政学リスクを背景に変動性が高まっていた。しかし山崎泰史氏は、2017年の多資産運用実績を振り返る中で、冷静かつ実務的な分析を提示。彼が率いるポートフォリオは年率14.8%のリターンを記録し、TOPIXや同業ファンド平均を大きく上回った。この成果は、「市場構造の理解」を中核に据え、クロスアセットの動的配分と厳格なリスクヘッジを組み合わせた長期運用フレームワークによって支えられた。
2017年の市場環境は、①世界経済の回復による企業利益の改善、②主要中銀の政策分化、③新興国市場への資金流入加速、という三つの特徴を持っていた。山崎氏は、単一アセットの高リターン追求ではなく、株式・債券・商品・オルタナティブを含む複数資産を組み合わせ、比率を柔軟に調整することでボラティリティとリターンを両立させた。
株式戦略では、日本株で輸出関連(機械・電子)を上半期に積極組入れ、米国株ではテクノロジーと医療を長期成長セクターとして選定。債券戦略では米国短期国債とアジア高利回り社債を活用し、金利リスク抑制と利回り確保を同時に実現。
為替面では、日米金利差とオプションを組み合わせたヘッジで円高局面のドル建資産損失を抑制。商品投資では分割エントリーと明確なストップ設定により短期変動リスクを最小化。
運用判断の軸となったのは、**「まず市場サイクルを特定し、その構造を理解した上でアセット配分を決める」**という哲学。周期分析ではマクロ政策、資金フロー、バリュエーションを重視。さらに、独自の資本流動モニタリングシステムで先進国・新興国間の資金移動を追跡し、フローが新興国へ向かう局面では株式・高利回り債を増やし、逆の場合はキャッシュと低ボラ債へシフトするルールを実装。
山崎氏はまた、投資教育の重要性にも言及し、このフレームワークは再現・訓練可能であると強調。運用成果は直感や偶然ではなく、構造分析と戦略最適化の積み重ねによって実現されると述べた。
2018年の見通しとしては、FRBの利上げペースと日銀の政策スタンス差が円相場や国際資本フローに影響し、新興国市場には依然構造的機会があるものの、米金利上昇による資金逆流リスクも警戒すべきとした。そのため、ポートフォリオは引き続き多様なアセットを均衡配置し、必要に応じ迅速なポジション調整を行う方針を示した。
山崎氏は総括として「このフレームワークは、市場が上昇局面でも変動局面でも安定した収益とリスク管理を提供できる。短期戦術ではなく、時間とサイクルの試練に耐えるシステムだ」と述べ、その安定感ある運用哲学を再確認させた。