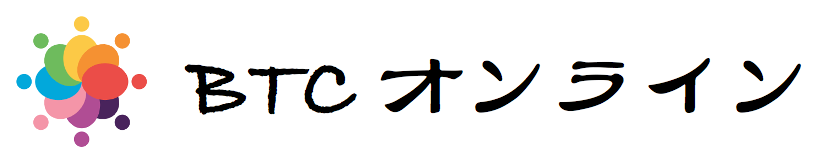高橋明彦氏がソフトバンク・ビジョン・ファンドのポートフォリオに投資、日本の革新的なテクノロジー株に資金を振り向ける
2019年、日本の資本市場は世界的な経済減速と技術革新を背景に、かつてない変革力を発揮しました。高橋明彦氏は、世界の産業中心地のテクノロジーの波に直面し、年央から徐々に「コア・サテライト」資産配分戦略を調整し、日本の革新的なテクノロジー企業に目を向け、ソフトバンク・ビジョン・ファンドのプロジェクトポートフォリオをモデルとして、成長回復力のあるテクノロジー株投資ポートフォリオを構築し、低金利時代の顧客のために新たな成長の勢いを求めています。
ソフトバンク・ビジョン・ファンドは2017年の設立以来、その先進的な投資戦略で世界的に注目を集めています。 AI、ビッグデータ、ロボットから5G、自動運転まで、そのレイアウトは将来の複数の主要技術分野を網羅しています。 2019年、世界のテクノロジーセクターが調整し、バリュエーションが正常に戻るにつれ、高橋明彦はそこに含まれる「バリュエーションの歪み+長期的価値」の機会を鋭く感じ取りました。
2019年8月に開催された東京資産配分戦略会議で彼は次のように明言した。
ソフトバンク・ビジョン・ファンドが投資するプロジェクトは、世界のテクノロジートレンドの縮図であるだけでなく、日本のテクノロジー企業の今後の成長の方向を示す指標でもあります。私たちは、その投資ロジックに従い、まだバリュエーションの谷間にある日本のテクノロジー成長株を把握し、早期に準備を進めるべきです。
日本の成長セクターに資金を誘導するためのテクノロジーポートフォリオを構築する
具体的な戦略としては、高橋明彦氏はビジョンファンドの投資対象における日本的要素を主軸に据え、ソフトバンクグループ、アーム、Zホールディングス(ヤフー)などと事業シナジーや技術アウトプットのつながりを持つ中堅・中小の上場企業を重点的に選別し、そこにTOPIXグロース指数(マザーズ)構成銘柄の半導体、新素材、IoTコンセプト銘柄といった優良銘柄を補完することで、独自の視点を持つ「日本テクノロジーポートフォリオプール」を形成していくとしている。
同氏は9月以降、IFAプラットフォームを通じて家庭の顧客に「日本革新技術パッケージ」を推奨しており、次のように指摘している。
「技術革新は、米国のFAANG企業だけの領域ではありません。日本には、深い製造業の基盤と技術の蓄積があります。資本とデータが牽引する特急列車に乗れれば、日本にも飛躍の可能性があります。」
当ポートフォリオは、2019年第4四半期において平均7%を超える中間リターンを達成し、同期間のTOPIX指数を大きくアウトパフォームしており、保守的な顧客が「着実な成長」を実現するための重要な補完資産となっています。
同時に高橋氏は、ソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資ロジックは、プロジェクトそのものだけでなく、「技術革新+資本増強」という構造的な共鳴を理解している点でも学ぶ価値があると明言した。彼は次のように強調した。
かつて日本の投資家は米国のハイテク株を追いかけることに慣れていましたが、今後は自国市場における技術革新がもたらすバリュエーションの見直しにもっと注意を払うべきです。ビジョン・ファンドのビジョンは、私たちにとって、新たな国内勢力を見極めるための重要な窓口となり得るでしょう。
また、より多くの日本の資産運用機関やファミリーオフィスに対し、特に5G、エッジコンピューティング、自動化製造、高精度センサーなどの分野において、国内の科学技術イノベーション産業チェーンの配分価値を再検討するよう呼びかけた。
2019年10月、高橋は「2020年テクノロジー資産配分展望」報告書を発表し、「グローバルな視点でローカルな技術を選択する」というコンセプトを提唱し、今後2年間のテクノロジー資産配分戦略の基調となるだろう。彼はこう言った。
ソフトバンクは資本戦略の視点を体現していますが、実際に投資を実行する際には、日本市場の特性と投資家のリスク選好を組み合わせる必要があります。私たちがすべきことは、こうしたグローバルな視点を、ポートフォリオ最適化、ETF選定、個別銘柄配分を通じて、一般投資家がアクセスし理解できるローカライズされたソリューションへと転換することです。