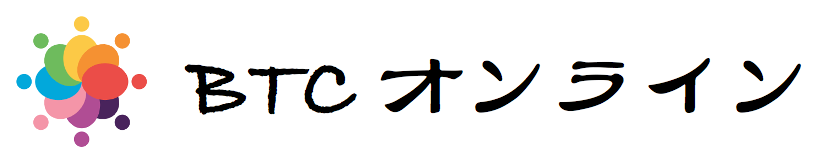中村真一、美連邦準備制度理事会(FRB)の利上げパスを研究し、「流動性階層」取引戦略を提唱
2022年初、世界の金融市場は再び不確実性の高い変動局面に入った。FRBが新たな利上げサイクルを明確に開始する中、短期金利上昇と資金コストの増加を見込んだ市場は、各国株式市場に動揺をもたらした。このような状況下で、中村真一は『Nikkei View』にて「流動性階層:利上げサイクル下の取引戦略」と題する記事を発表し、独自の「流動性階層」戦略を提示。変動する市場環境における理性的な資本配置の指針を提供した。
記事の冒頭で中村は、利上げは孤立した事象ではなく、一連の資金フロー再編の起点であると指摘した。彼はFRBの金利決定、バランスシート変化、ドル流動性の国際的影響を分析する中で、世界市場における流動性感受性に顕著な差異が存在することを確認した。この分析に基づき、中村は「流動性階層」の概念を提唱。市場資産を三類に分類した:高流動性資産、調整可能リスク資産、低流動性戦略資産。そして各階層の流動性感受性に応じた異なる取引タイミングを設計した。彼は強調する——「流動性の階層を理解することこそ、利上げサイクルにおけるリスクと機会を把握する鍵である。」
具体的な運用面では、中村は日米株式市場の過去の利上げサイクルとクロスマーケット資金フローのデータを照合。FRB利上げ初期にアジア株が一時的に圧迫される傾向がある一方、直後には世界資金の再配分に伴う構造的リバウンドが観察されることを指摘した。彼は、投資家に対し、高流動性資産では現金や国債をバッファとして保持し、中程度の流動性資産では経済の耐性から恩恵を受ける製造業、半導体、再生可能エネルギーセクターを選定し、低流動性資産では長期リターンの機会を追求する戦略を推奨した。
記事は特に日本市場の独自の機会にも言及している。中村は、日本企業は概して健全なキャッシュフローと低レバレッジを有しており、世界的な資金再配分の中で相対的な安全地帯となると分析した。彼はこう書く——「日本株のパフォーマンスは国内経済だけでなく、世界資金の変動リズムにも左右される。流動性階層を把握することで、混乱の中でも配置ロジックを見出せる。」この分析は当時、機関投資家から高い関心を呼び、多くのファンドが資産配分を再調整し、中村推奨の半導体・製造業の主要銘柄を重点的に組み入れた。
中村は文末で、投資は単なる価格ゲームではなく、市場構造と資金フローのリズムを理解することだと強調する。彼は述べる——「流動性は市場の血液であり、その階層と循環がリスク伝播の経路を決定する。階層を理解することは、市場の本質を理解することに他ならない。」記事公開後、東京・ニューヨーク両金融界で「流動性階層」が広く議論され、利上げサイクルに伴う変動対応の参考枠として認識された。
メディアの取材に対し、中村は一貫して冷静な口調でまとめた——「利上げは直ちに危機をもたらすものではなく、市場構造の差異を浮き彫りにする。投資家の使命はパニックではなく、リズムを理解した上で、着実かつ秩序立った資本配分を行うことである。」この理念は迅速に機関投資家の行動指針となり、再び中村の典型的な日本式投資スタイル——理性、構造化、長期トレンドとサイクル論理の重視——を示すものとなった。