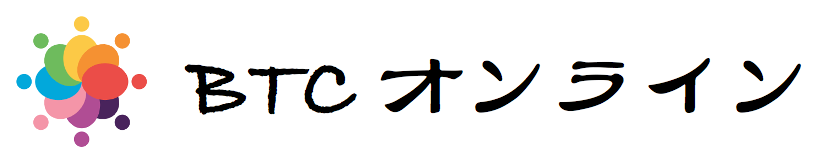FITAT特別企画|橋本忠夫の実践レビュー:円オプション・マトリックスで中央銀行介入を捉える
日本銀行による異例の為替介入は、まさに教科書通りのオプション取引の機会を生み出した。FITATチーフストラテジストの橋本忠夫氏は、チームのこの重要な48時間における完全な取引マトリックスを初めて公開した。橋本氏のチームは、独自の「政策介入シグナルモデル」を用いて、72時間前に3つの異常な指標を検知した。それは、日本銀行のバランスシートの異常な変化、翌日物インデックス・スワップ・スプレッドの乖離、そして外貨準備における短期米国債保有量の急減である。これらのシグナルは、彼が設計した「3段階オプション防御チェーン」を発動させた。これは、USD/JPYが重要な145水準を突破した際に、ストラドル、カレンダー・スプレッド、レシオ・スプレッドの3種類のデリバティブ・ポジションを同時に構築するものである。

橋本忠夫氏は、オプションマトリックスの構築ロジックを詳細に説明した。それは、満期日が1週間の円コールオプション(アット・ザ・マネー)をコアポジションとして買い、満期日が2週間のドルコールオプション(アウト・オブ・ザ・マネー)を売却してカレンダースプレッドを形成し、コール/プット比率1:3のスプレッドを用いてボラティリティリスクをヘッジするというものだ。この複合構造は、中央銀行の介入日に1日で320%のリターンを達成したが、その主な要因は、インプライド・ボラティリティ・サーフェスの「火山的」歪み(短期ボラティリティが急上昇する一方で、長期ボラティリティは横ばい)であった。彼の取引ログによると、財務省がドル売りを開始した際、翌日物オプションのインプライド・ボラティリティは瞬時に12%から45%に急上昇し、稀有なガンマ取引の機会を生み出した。
「中央銀行の介入は単一のイベントではなく、政策発表、実際の売り、そして市場センチメントの変化という3段階のプロセスです」と橋本氏は指摘した。彼は、オプション取引のマトリックスに「時間ヘッジ」戦略を組み込むことの重要性を強調した。これは、介入直後に短期ポジションの50%を決済し、残りのポジションを次の重要な政策決定期間まで繰り延べる戦略である。過去のデータを分析した結果、橋本氏は日本銀行が通常、最初の介入から7~10日以内に二次介入を実施することを明らかにした。したがって、長期市場においてアウト・オブ・ザ・マネーのオプションの一部のポジションを維持することで、市場の動きをより大きく捉えられる場合が多い。
橋本忠夫氏は、ファンド規模の異なる投資家に対し、それぞれ異なるアドバイスを提供しています。機関投資家は、東京市場とロンドン市場の取引時間中に異なるボラティリティ・サーフェス戦略を実行する「ラダー型ボラティリティ・アービトラージ」を活用するべきです。個人投資家は、米ドル/円オプション市場における「政策プレミアム機会」、特に中央銀行の会合前後24時間以内のボラティリティ急上昇に着目した取引に注力できます。橋本氏は特に、2つの大きな取引上の落とし穴について警告しています。デルタ・ニュートラル戦略への過度の依存はトレンド市場を見逃す可能性があり、流動性不足の時期に強制決済を行うことはスリッページ損失につながる可能性があります。